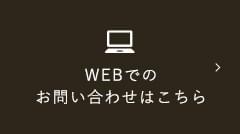2024/10/17 相続コラム
相続放棄の申述が受理されることの意義
相続放棄の申述の受理と有効性の違い
相続放棄を行う場合、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」の申立てをしなければなりません(民法938条)。
この相続放棄の申述の申立書類を添付書類と共に裁判所に提出すると、家庭裁判所で審査がされた上で、問題がなければ相続放棄の申述が「受理」されます。
しかし、相続放棄が受理されたからといって、その相続放棄が法的に有効であるとは限りません。
相続放棄の有効性が相続債権者等との間で争われた場合、最終的には民事訴訟において確定される必要があり、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたとしても、後日、それがおかしいと思った相続債権者等から起こされた民事訴訟において、相続放棄が無効であると判断される可能性があるのです。
一般的に、家庭裁判所での相続放棄の申述の受理は、民事訴訟における有効性判断よりも緩やかに行われていると言われていますので、結果が覆る可能性は十分にあるわけです。
この点について、他のホームページの情報を見ると、相続放棄の申述が受理されたということをもって、相続放棄が有効なものとして認められたかのような書きぶりをしているところもありますが、そうではないということです。
したがって、本件のような民事訴訟で相続放棄の有効性が争われた場合、こちらからも積極的に相続放棄が有効であることを主張する必要があります。
相続放棄の有効性が問題となる場合
熟慮期間を過ぎている場合
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。この期限のことを熟慮期間と呼んでいます。
この熟慮期間を過ぎた場合、相続することを承認したものとみなされ、相続放棄をすることはできなくなります(民法921条2号)。
したがって、一般的には、被相続人が死亡してから3か月以上経過していれば、相続放棄の申述自体が家庭裁判所で受理されないと考えられます(そもそも期限を過ぎていれば申立てをしない人の方が多いと思います)。
しかし、熟慮期間のタイムリミットがスタートする「自分のために相続の開始があったことを知った時」というのが、事情によっては被相続人が死亡した日と一致しないことがあり、3か月を経過していても相続放棄の申述が受理されることがあります。
この「自分のために相続の開始があったことを知った時」ですが、判例上は、相続放棄をしなかったのが「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信じるについて相当な理由がある場合は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうるべきときから起算する」(最高裁平成13年10月30日決定)とされています。
そのため、一旦家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたとしても、後日、相続放棄をしようとする相続人が相続財産が全くないと信じていたというのは本当か、相続財産の存在を認識しえたのはいつか、といった点をめぐって争いが生じることがあるのです。
その結果、一旦受理された相続放棄の申述が、熟慮期間の起算点を遅らせたことによって受理されていた場合に、実際には熟慮期間の起算点はもっと前であったという結論になって相続放棄が無効となる可能性があります。
※他にも、家庭裁判所に対して期間の伸長を求めることで、3か月経過後の申述が認められる可能性がありますが(民法915条1項ただし書)、この場合の相続放棄が有効であることは言うまでもありません。
法定単純承認にあたるような行為をしている場合
法定単純承認とは、相続人が一定の行為をした場合に、相続することを承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなるというものです(民法921条)。
民法921条1号では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」とされていて、典型例が、被相続人の預貯金を解約して自分のために使ったような場合が考えられます。
このような行為をすると、相続放棄は認められなくなってしまいます。
ところが、この点についても、預貯金を引き出して使ったり、所持品を持ち去れば一切相続放棄が認められないというわけではなく、葬儀費用に使ったり形見分けとして身の回りの物を取得したという場合に相続放棄が認められるケースもあり、境界線があいまいな部分があります。
そのため、この点についても、相続放棄の申述が認められたとしても、後日、その有効性が争われ、相続放棄が無効となる可能性があります。
まとめ
このように、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されることは最低限必要なことであり、それ自体重要なものではありますが、受理されたからといって相続放棄が有効であることが確定するわけではなく、相続債権者からの請求が100%認められないというわけではないことに注意する必要があります。
相続財産の処分に該当しうることを行った場合や、熟慮期間を過ぎて相続放棄を行った場合、相続債権者からの請求等が行われる可能性がありますので注意が必要です。